- 損益通算ができない。
- 株や投資信託を解約した際、非課税枠は復活するが、同年中には復活しない。
先日、とあるお客さまから新NISAについて聞かれたことについて、備忘もかねて書いておく。
使い勝手のよい新NISAだが、以下2点には気をつけておきたい。
新NISA分は損益通算ができない
損益通算と繰越控除
本来、株式や投資信託から得られた利益には、およそ20%の税金がかかる。
一方で、必ずしも運用がうまくいくとは限らず、利益よりも損失が大きくなる年もあるだろう。
ただし、損益にかかわらず利子や配当は得られるケースが多く、その利子や配当にも20%の税金がかかるわけだが、発生した損失額を、その年の利子や配当額と相殺することができる。これが損益通算だ。
さらに、損失額が大きく、利子や配当で控除しきれなかった場合は、翌年以降の利益とも相殺でき、3年間にわたって損失額を控除することができる。(繰越控除)
新NISAでは損益通算ができない
新NISA口座で運用する株式や投資信託においては、損益通算ができない。(つまり繰越控除もできない)
これは旧NISAでも同様であったが、今一度認識しておこう。
新NISA口座のみで運用している人にはあまり関係ないが、特定・一般口座でも運用していて、かつ確定申告をしている人にとっては要注意だ。
極端にいえば、新NISA口座では利益を出さないと意味がない。リスクの大きい株式やファンドをよくわからずに購入し、大きな損失を被ってしまうと税制面でもデメリットが大きいので、そこは注意しよう。
売却した分の非課税枠は、翌年に復活する
これもうっかり忘れがちなので、今一度確認されたい。
新NISAの使い勝手のいい点の一つが、新NISAで購入した株式や投資信託を売却した際、また非課税枠が復活する点だ。
そもそも、非課税枠の消費については、投資した金額で計算される。例えば、100万円を投資して、その後300万円に値上がりしたとしても、新NISAの非課税枠は100万円のみ消費されることになる。
よって、上記の例でいえば、300万円に値上がりしたのちに売却した場合、100万円の非課税枠が復活することになる。
ただし、非課税枠の復活は翌年以降になる点に注意だ。
そもそも新NISAは長期投資に向いている制度だ。短期間で頻繁に売買するようなケースにはあまり向いていないことを認識しておこう。
まとめ
新NISAはメリットが多く、使い勝手がいいのは間違いない。
ただし、新NISAの非課税枠を超える金額で運用する(すでにしている)方や、株式等を頻繁に売買される方は、上記のデメリットについて要注意だ。
新NISAでは、つみたて投資枠ではもちろんのこと、成長投資枠においても、基本的に解約を前提としない長期投資に適した銘柄やファンドを選ぶといいだろう。
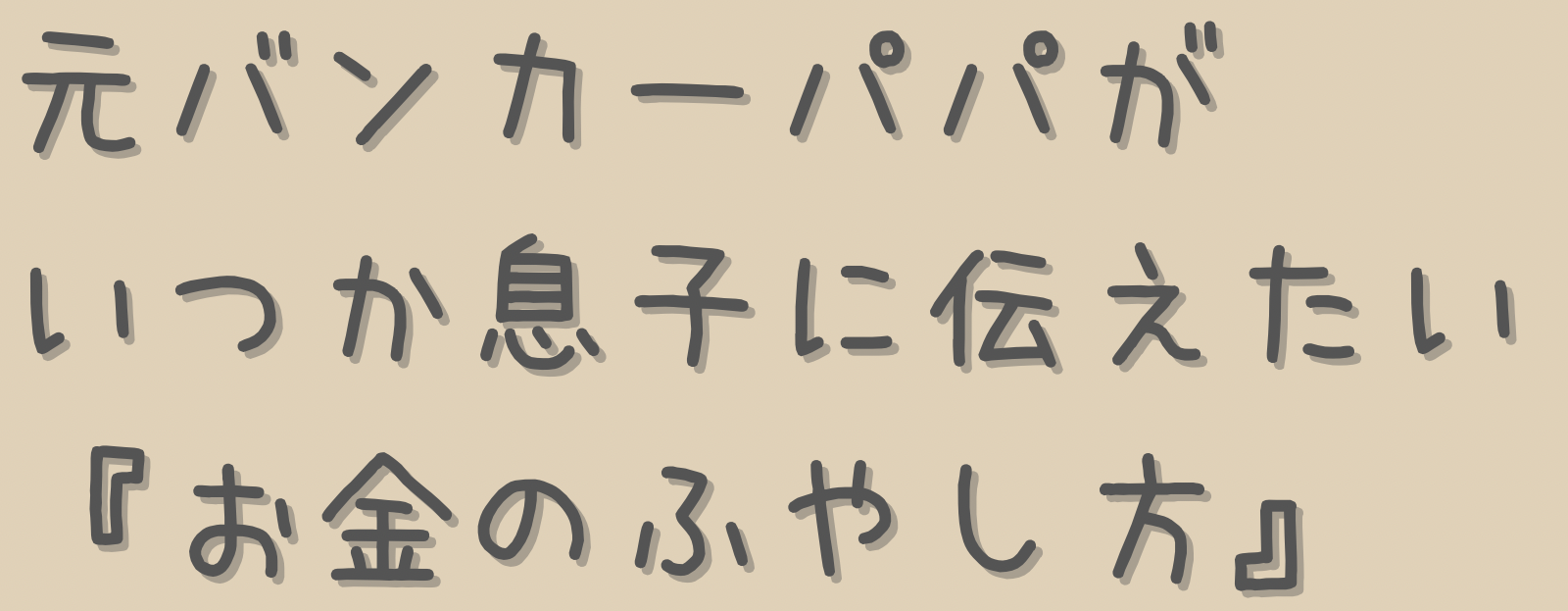
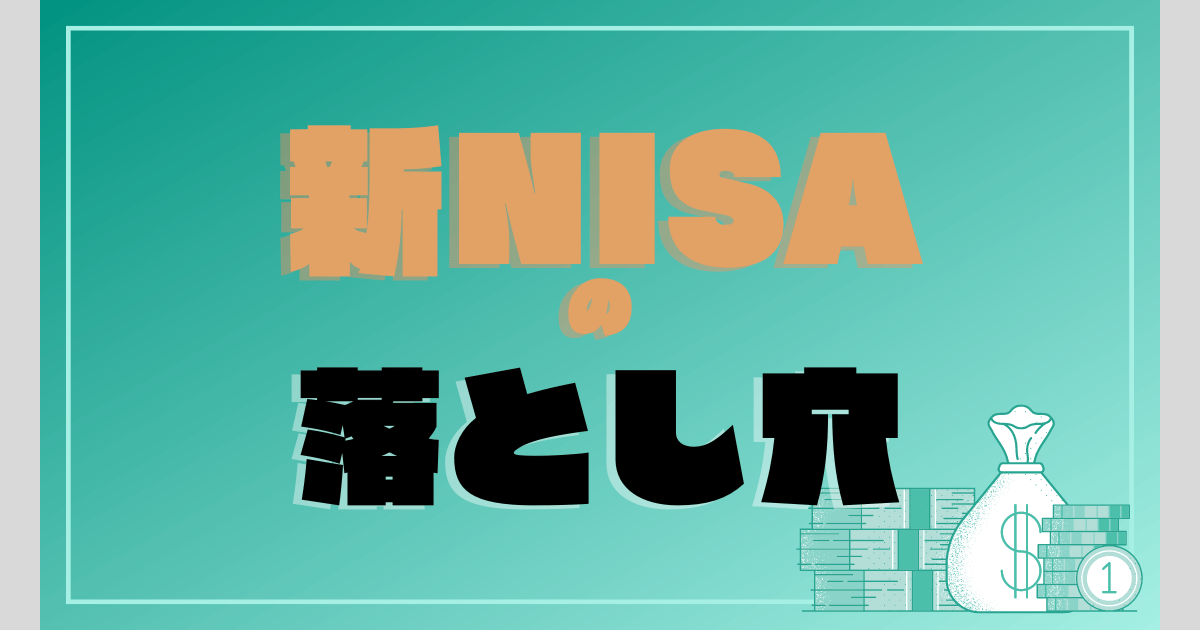
コメント